今回は大学院受験のために必要な研究計画書などについてお話します。
大学院へ進学するために用意した資料の中でいくつかをピックアップ!
専門卒の方は、出願に先立ち出願資格審査を行うため、事前に提出する資料もありますので、大学院の募集要項を熟読することをお勧めします。
よって、全ての大学院に当てはまるとは限りませんのであらかじめご了承ください。
募集要項を熟読|必要な書類
まず大前提に、出願を希望する大学院から出ている「募集要項」を熟読することから始めましょう。
その中でも、個人的に苦労した資料をいくつかピックアップします。
チェック
- 成績証明書
- 研究計画書
- 研究歴・研究従事内容証明書
他にも、志願表や受験票、卒業証明書などがありましたが、これらは問題なく収集・作成することが出来るかと思います。
今回ご紹介するものは、時間があれば問題なく資料を準備・作成できるかと思いますが、私の場合土壇場で「大学院への進学」を決意したので、スケジュール的にはとてもタイトでした。
それではひとつずつ見ていきましょう。
成績証明書
出身大学(学部)が作成した「成績証明書」を求められることが多いかと思います。
これ自体は、受験者自身が作成するということはないかと。
ただひとつ問題点が…。
時間がかかる
私自身簡単に考えていましたが、母校に成績証明書の作成を依頼し手元に届くまでに、なんだかんだで1-2週間かかりました。
また、成績証明書の作成・送付まで結構金額がかかるので、予想外の出費も強いられます。
- どれだけの期間がかかるのか?
- どれだけの費用がかかるのか?
母校に尋ねてみるのもひとつかと思います。
研究計画書
今回の提出書類の肝と言える、1番重要な書類です。
何と言っても
「私は、大学院で〇〇について研究したい。なので、△△教授のもとで研究したい。」
という意思表示であると考えます。
研究計画書とは、「大学院入学後に行いたい研究内容と、その研究を行うための計画について、大学院・研究科側の所定の様式に従ってまとめたもの」と定義することができます。研究計画書は①研究内容、②その計画から成り立つものであると考えてください。
※河合塾KALSより引用
志望した大学院を受験する理由として、こんなものに興味を持っている・こういう研究がしたいなどとという「テーマ」があるかと思います。
その研究テーマが、教授とマッチしているのか?指導可能なのか?をこの研究計画書で確認することになります。
この研究計画書を提出する前に、指導を希望する教授と事前の面談が必要なケースが多いかと思います。
その際に「ズレ」がないか確認します。
研究計画書もただつらつらと単語並べるだけでなく、タイトルから目的・方法・研究の背景・予想される結果・引用文献などについて構成します。
ここまで説明すると、もう気付かれているかと思います。
作成に時間がかかる
ましてや「テーマ」が定まっていない場合は、より時間がかかるかと思います。
なぜ大学院へ進学するのか。
改めて考え直す時間にもなるかもしれません。
まとめ
- 教授の専門分野とマッチしているのか?
- 教授が指導可能なのか?
- ズレがないのか?
研究歴・研究従事内容証明書
これまで行ってきた研究歴を大学院側へ提出するものです。
専門卒の私にとって、大学院側にアピールできる数少ない材料でもあります。
前回少し触れましたが、大学を卒業した者と同等以上の学力として認められるために、以下の項目をこの研究歴・研究従事内容証明書に記す必要があります。
ポイント
- 著書
- 学術論文
- 研究発表
- 特許
今までの業績を羅列し、書類のフォーマットに当てはめていく作業をしていきます。
しかし、ここで注意すべきは私が専門卒の場合だということ。
もし、大学を卒業した方であるならば、この書類に求める目的は大きく異なる可能性があります。
最後に
今回は「大学院受験のために必要な研究計画書など」についてお話しました。
出願に係る書類の作成に一番四苦八苦したのが研究計画書です。
もちろん研究するテーマを文字で起こすことも大変ではありましたが、「なぜ大学院へ進学する必要があるのか?」分を、改めて自分自身に問いかけるいい機会になったかと思います。
個人的には、母校に作成して頂いた成績証明書を開封したい衝動を抑えるのに苦労しました(笑)。
おわり!
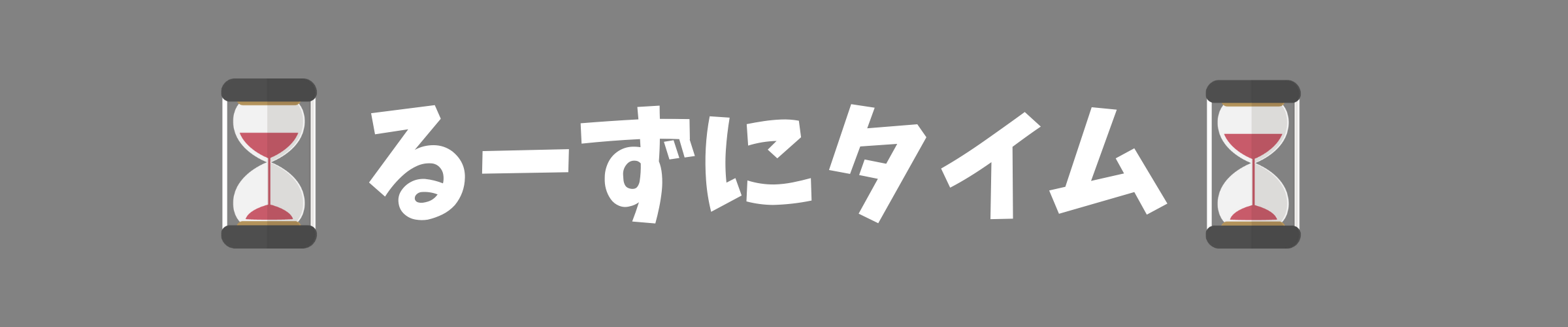

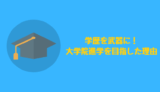
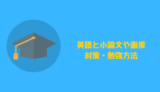
コメントを残す